画像生成エージェントで社内資料作成を効率化。ChatAIの活用で従来できなかった業務も対応可能に。
鉄やセメント、非鉄金属などの製造に用いられる工業炉に欠かせない耐火物の総合トップメーカーである「株式会社ヨータイ」(以下、ヨータイ)。1936年の創業以来、日本のものづくりを支えてきた同社は定形耐火物の国内生産量トップクラスを誇り、常にお客様のニーズに柔軟かつ迅速に応え続けている。同社では、耐火物の製造・販売のみならずエンジニアリング事業も展開しており、材料の提供から工事まで一貫して担えることを強みとしている。
社内にはDX推進プロジェクトを設け、「まずやるDX」というスローガンのもと、全社的なデジタルトランスフォーメーションを推進している。生成AIが急速に普及する中、同社は社員の個人利用によるセキュリティリスクや、効率化余地のある日常業務といった課題に直面し、その解決策として「ユーザーローカル ChatAI」(以下、ChatAI)を選定した。現在では、当初想定した社内規則の検索にとどまらず、翻訳やメール作成、プログラミング、経営層の意思決定支援まで、活用範囲は多岐にわたる。本記事では、ChatAI導入の背景から具体的な活用方法、導入によってもたらされた成果などについて、お話を伺っていく。

本社業務部総務グループ 西尾 さやか
本社業務部情報システムグループ 吉長 旭
本社業務部総務グループ 河原 一仁
導入背景
膨大な社内規定ファイルから知りたい内容を探すのに時間がかかっていた
コスト・最新モデルへの対応・使いやすさが導入の決め手に
国内外の基礎産業と共に発展し、現在も耐火物の総合トップメーカーとして人々の生活を支えているヨータイでは、変化の激しい時代に対応すべく、DXへの取り組みを積極的に進めている。社内ではDX推進プロジェクトを設けて各部門からキーマンを選出し、DX化や生成AI活用を進めるプロジェクトが始まった。吉長氏は「2024年に入った頃から生成AIに関する議論が始まりました。今後は、生成AIをうまく活用することが前提になるだろうという考えもあり、『ヨータイも乗り遅れないように生成AIを取り入れよう』というのが出発点でした。まずは導入してみて、その上でどう活用できるかを考えていこうという意識が強かったですね」と、当時の状況を語る。
生成AIの導入をするにあたり、看過できない課題が2つ浮上した。1つはセキュリティリスクである。一部の社員が個人でChatGPTのアカウントを取得し、業務に活用し始めていたのだ。「個人のアカウントで社内の実績データが含まれたファイルを生成AIに読み込ませ、データ集計を依頼するようなケースが見受けられました。確かにExcelやPDFのデータを手作業で集計すると時間がかかるだけでなく、入力ミスといった懸念もあります。生成AIを活用すれば業務を効率化できると感じていたので、安全に使える環境を整えることは急務でした」と吉長氏は振り返る。
もう1つの課題は、社内の情報検索における非効率性だ。ヨータイの社内規則は、旅費規程や家賃補助、育児休暇に関するものなど、項目ごとに100以上のWordファイルに細かく分散している状態だった。「ある規則を知りたくても、どのファイルを見ればいいのか探すのに時間がかかりました。例えば家賃補助について調べる際、メインの規則ファイルだけでは具体的な金額が分からず、補助を受けられる条件が書かれた別の細則ファイルを探す必要がありました」と吉長氏。

これらの課題を解決すべく、同社は生成AIツールの導入に動いた。その際に求めていた条件は、セキュアな環境で使えることと、社内規則を全て読み込ませることができる十分なRAGの容量だ。この条件を満たしたツールを比較する中で、ヨータイがChatAIの導入に至った決め手は「全社展開可能なコストパフォーマンス」「最新モデルへの対応」「優れたUI」の3点だという。
「ChatAIは全社展開を想定してもコストを抑えられることがわかり、費用対効果に優れていると感じました。加えて、最新の言語モデルへの対応が非常に速いことも魅力的です。私たちのような製造業では、図面や数値を用いた計算業務も多いため、推論モデルの活用は必須です。当時はちょうどGPT-4oのような推論モデルが出始めたタイミングだったので、最新のモデルが使えることで、より業務に活用できる幅が広がると考えました」と吉長氏は語る。
最大の決め手となったのは、トライアルで実感したChatAIの使いやすさだという。トライアルで積極的にChatAIを使った吉長氏は「トライアルの時点でChatAIの使いやすさを感じました。一般に公開されているChatGPTと似たようなUIなので、個人でChatGPTを使った経験がある人には詳しく操作説明をする必要がありません」と教えてくれた。
コストが抑えられることに加えて機能やUIも優れていると感じたことから、ヨータイでは社内決裁も円滑に進み、ChatAIの正式導入が決まった。
活用方法
株主総会の想定問答作成から日常のメール作成など活用範囲は多岐にわたる
画像生成エージェントで、展示室のイメージ写真を瞬時に生成
スムーズに導入が進んだというヨータイでは、まず、DX推進プロジェクトメンバーにアカウントを付与し、その後、経営層にも生成AIを使える状態にするために、部長以上全員にアカウントを付与した。さらに、希望者にもアカウントを配り、徐々に口コミが広まって利用者が増えているという。
導入後の利用を広めるために、ユーザーローカルによる勉強会を開催した。アカウントを付与した部長以上を対象にしたが、希望者の参加を可能とし、内容は録画して後から社内で見返すことができる環境を整えた。吉長氏が「勉強会の後は、ドキュメントを活用した利用が増えました」と語るように、勉強会の効果は確実に表れている。
「勉強会では、決算短信をChatAIに読み込ませ、株主総会などで想定される質問を作成することも可能であるという具体例を紹介し、『こういった使い方もできるのか』と興味を持ってもらうことができました」と吉長氏は語る。
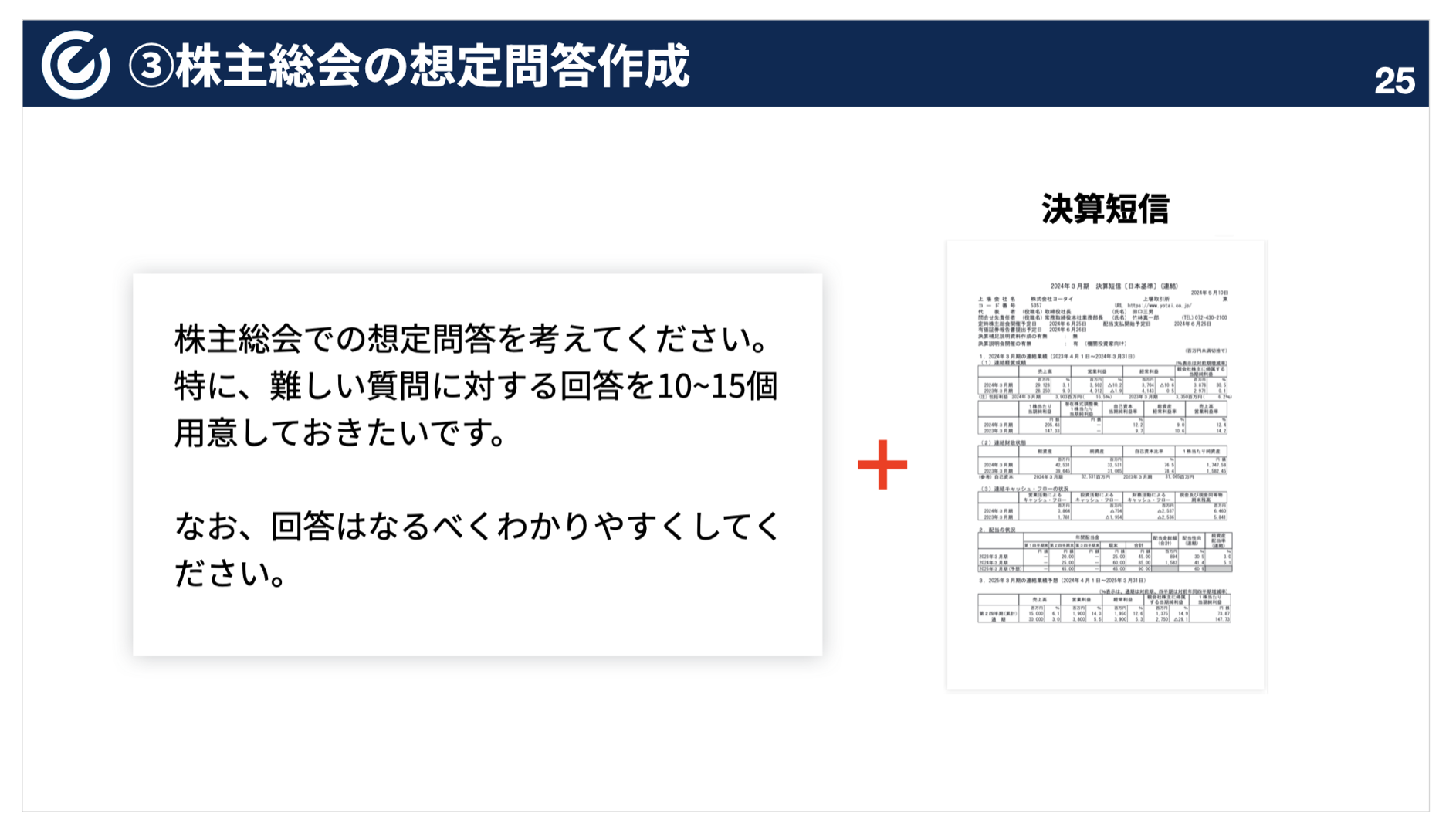
また、海外とのやり取りが多い営業部門では、翻訳の用途で使われる場面が目立っている。「営業担当者が海外メーカーのカタログや安全シートの翻訳・要約にChatAIを使っているケースが多いですね。語学が堪能な社員でさえ、翻訳精度の高さに感心し、今では業務効率化に欠かせないツールとして活用しています。ChatAIを使わなくても海外の資料を把握できるスキルがあったとしても、文章に目を通して内容を理解し、要点をまとめる作業は避けられません。一度ChatAIの精度が高いとわかれば、いきなり翻訳・要約を出力して作業を完結させられます」と吉長氏。翻訳については、外国語でメールのやりとりをする際にも活用されているそうだ。
ヨータイにおいて、幅広い部署で使われている方法に「メールの文面作成」がある。社内外問わず、どの場面においても活用されており、受信したメールを読み込ませて返信内容を作ってもらう人もいれば、自分が伝えたいことを箇条書きでまとめて文面を作ってもらう人もいるようだ。
よくメール作成でChatAIを活用するという西尾氏は、「社内向けに親しみやすい文面・かしこまった文面を作ってもらうテンプレートと、社外向けに丁寧で信頼感がある文面を作ってもらうテンプレートを活用しています」と、場面に応じて生成される文章の雰囲気を使い分けていることを教えてくれた。
さらに社内報の作成を担当する西尾氏は、記事の構成やリライトにもChatAIを活用している。「出来上がった記事を校正してもらったり、読者を引きつける見出しを何パターンか提案してもらったりしています。掲載スペースの都合で記事を短くする必要があるときも『この記事を100字程度に要約して』と頼めば、趣旨を保ったままコンパクトにしてくれます。一から考え直す手間が省けるので、非常に助かっています」と西尾氏。
ヨータイではエージェント機能も積極的に活用しており、道前氏は画像生成が特に役立っているという。「2026年の創業90周年に向けて展示室の設置を計画しており、そのレイアウトデザインを画像生成AIで具体的なイメージ図として作成する試みも行っています。例えば、展示室にする予定の会議室の写真を撮り、『この壁にパネルをかけたイメージを作ってほしい』とAIに指示すると、すぐに精度の高いイメージ画像が生成されます。完成後の姿を視覚的に共有できるため、関係者の意見をまとめやすくなり、計画がスムーズに進みます」と道前氏は語る。

続けて道前氏は「ChatGPTで画像生成をすると、1枚の画像を作るのに数時間かかってしまうこともあります。しかし、ChatAIだと早ければ数十秒で生成されるので、素早くブラッシュアップをかけられます」と効果を教えてくれた。
効果・成果
ChatAIの活用で従来できなかった業務も対応可能に
「何かあってもAIに相談できる安心感」が醸成された
ChatAIがもたらした効果は時間短縮にとどまらず、本来できなかった作業ができるようになった変化もあるようだ。例えば、専門知識がなければ不可能だったプログラミングやデータ加工について、専門知識がなくても実行できる環境になった。
「私はプログラミングが専門ではないため、PythonやJavaScriptを一から書くことはできません。しかし、その足がかりとなるCSVファイルを読み込ませて『ワイドデータをロングデータに置き換えるPythonのコードを組んでください』と指示するだけで、すぐに叩き台を生成してくれます。その後は自分で必要な箇所を修正すればよいですし、エラーが起きても原因をChatAIに聞くことができます」と吉長氏は効果を教えてくれた。
ChatAIの導入は、社員にとってAIが身近な存在となるきっかけにもなっている。河原氏が「パソコンを立ち上げたらすぐにChatAIを開きます」と語るように、「まずAIに相談できる安心感」が生まれている。「これまではどのようなキーワードで検索すべきか分からず諦めていたような曖昧な疑問でも、ChatAIには自然言語で質問できるため、圧倒的に使う頻度は高いですね」と河原氏は語る。
着実に成果を上げる中、ヨータイは活用の幅を広げることを視野に入れている。「まずは、全社員が生成AIを使える環境を整えたいですね。現在は希望者にアカウントを配布していますが、今後は全社展開を計画しています。また、全社向けの勉強会や、各地の事業所を直接訪問しての個別説明会などを通じて、より深い活用を促していきたいです」と吉長氏は今後の展望を語る。
利用申し込み
- 同業企業様、学生の方のお申し込みはご遠慮いただいております。
- フリーメールアドレス(GmailやYahooメール等)はご利用いただけません。
- 弊社担当より製品説明会や勉強会などのご案内の連絡をさせていただくことがあります。
- ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー
- このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。
プライバシーポリシー ・ 利用規約